
マイストア
変更
お店で受け取る
(送料無料)
配送する
納期目安:
05月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
正式的 Amazon.co.jp: 本煎茶道三癸亭賣茶流故島村石心先生追善茶会記 施釉陶の詳細情報
Amazon.co.jp: 本煎茶道三癸亭賣茶流故島村石心先生追善茶会記。Amazon.co.jp: 本煎茶道三癸亭賣茶流故島村石心先生追善茶会記。はなの玉手箱:全国煎茶道大会 黄檗山萬福寺@三癸亭賣茶流。長崎県産ヒノヒカリ。 閉じる
絶版希少本 非売品
閉じる商品説明に画像多数掲載。 画像の後に、商品説明がございます。
非売品 煎茶道 三癸亭賣茶流 故島村石心先生追善茶会記 写真集
1982年
フルカラー
31*22*2cm
函入 銀箔押し布張り上製本
※非売品
※絶版
煎茶道・三癸亭賣茶流煎茶道家元故島村石心先生追善大大茶会の茶会記のすべてを、フルカラー写真で紹介、
茶会記には、煎茶席の主題趣向についての解説、使用したすべての道具の名称を記載。
【結びのことばより】
故石心の一周忌に当り、諸先生方の御協力により、盛大なる追善茶会を催して頂き、厚く御櫃申し上げます。
ここに計らずも今後賣茶流が更に大きく発展して行く原動力が芽生えた訳であります。今後この新しい芽が大きな枝となり、幹となって成長して行くことを希望する次第であります。
同参列、本堂内陣左側に遺族親族、右側に来賓席を設け、本堂に流門の各地区代表等約200名が着席して定刻にお寺の半鐘を合図に津曲岩人氏の司会により開式。先生は94歳の高齢で、淡、としたお手前で然も厳粛に、香、菓子、茶が祭壇の遺杉の前に捧げられ、一同感激して礼拝。
黄檗宗管長村瀬玄妙猊下御列席について
故仙友宗匠は四十九代管長玉田和尚の時、黄檗山に参山修業して得度を受けておられますが、現村瀬管長はその時の御法友と伺っております。
この度の追善茶会に御案内申し上げましたところ、非常にご多忙なご日程の中を、お繰り合せになり。
供茶式で焼香を済まされてからも、各茶席に入席され、特に入船山席では法話を項いて、参列者一同大いに感激いたしました。本堂席に入りますと、床には石心先生画賛巖図、向って右の花生は古染萬暦有環、左に唐物の念珠箱(菩提樹珠数)が置いてあります。石心先生画の岩と活けました蘭で雅題が幽谷遺響となりますのでこれを銘とし、菓子は生前先生の好まれた麦落雁で型を充石先生に好んでいただき、萬の徳あつまれる姿をもって石心先生の遺徳香しきをあらわし、萬徳と決めていただきました。
茶具は左記の通りです。朶は花のついた枝、多くの花技が佳き友を招き、ひとすじの雲(茶畑)が石樓に上っている。扇面は唐の李白の七言絶句「早發白帝城」、
朝辭白帝彩雲間 千里江陵一日還
両岸猿聲啼不住 軽舟已過萬重山
朝に辭す白帝彩雲の間、千里の江陵一日にして還る
両岸の猿聲啼いて住まらず、軽舟已に過ぐ萬重の山
朝早く白帝城のもと辰光に染まる雲を兄て立ったが、一日にして千里下流の江陵(地名)まで還ってきた、両岸の猿の聲がきこえたと思うそのうちはや、軽舟は高取の山の間を通りすぎていたことだった。
第三席は夕顔棚普通式席で、まず床は、正面に中林竹洞画の嵐山の翠したたる図、右に古木の器に竹と萬年青、霊芝及び左に置いた太湖石とで萬年如意となっております。
茶具
炉塀 石心先生画山水
涼炉 白泥泥中庵蔵六造
台 黄交趾仝右
湯沸 唐物黄交趾
静沸 時代籐組
茗碗(茶碗) 唐物染付
替 石心先生書
托子(茶托) 唐物古錫菊花式
替 石心先生書
急須 唐物朱泥
一文字 黄揚木
缶台 仝右
水注 白磁清風造
茶心壺 唐物古錫八角式
茶合 唐物時代彫
服紗 時代更紗
巾容(巾筒) 古染付
盆巾入 唐物籠網代組
落葉壺(建水)鉄砂竹軒造
烏府 唐物竹組
火筋 時代砂張
羽箒 青鸞羽
菓子器 古染付蓮花文
替 色絵遊蝶文竹泉造
菓子箸 白竹宗拶作
茶銘 百禮
菓銘 以洽
●入船山記念館
門聯は賣茶翁の句、亭を開いて海内の君子を抜き、茶は熟して人間の睡魔を駆す、でございます。まず第一室の床は石心先生書、到此方知滋味別、此に到って方に滋味の別なるを知る、左に時代唐物水差を置き菊を活け、右に銅器の蟹を配して雅題を華甲と致しております。付書院前には先生作の愛用の机、常用の文房具及び、先生書寿字百体帖、床脇の棚には先生が黄檗にて得度された時の記念の絡子、先生常用の茶具と先年東京大会にて発表されました竹泉造の茶碗五客、地板の上には先生書入れの茶具、床脇の前にこれもやはり先生常用の茶具類と先生書の袱紗を配しました。また。
尚、本席の茶銘菓銘は雄峰と蓮座でございますが、これは掛軸の句より茶銘雄峰を、独座より蓮の台に坐ることを想起して菓銘とさせていただきました。古本特有の古びたにおいがそれなりにあります。(見落としはご容赦ください)
★状態★
外観は通常保管によるスレ程度、目立った書込み・線引無し、
問題なくお読みいただけると思います。
古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。
■中古品です。
モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。
■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。
■PCよりの出品です。
■かんたん決済支払期限が切れた場合、連絡が取れない場合、
落札者都合にてキャンセルいたします。
他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。
誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。
★商品の状態について★
ヤフオク!の定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。
新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品
未使用に近い…中古ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない
目立った傷や汚れなし…中古品。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある
全体的に状態が悪い…中古品。ジャンク品など。本煎茶道歳時記当代最高位の家元宗匠茶会記解説47席盛物涼炉水注。
ベストセラーランキングです
近くの売り場の商品
カスタマーレビュー
オススメ度 4.3点
現在、4223件のレビューが投稿されています。

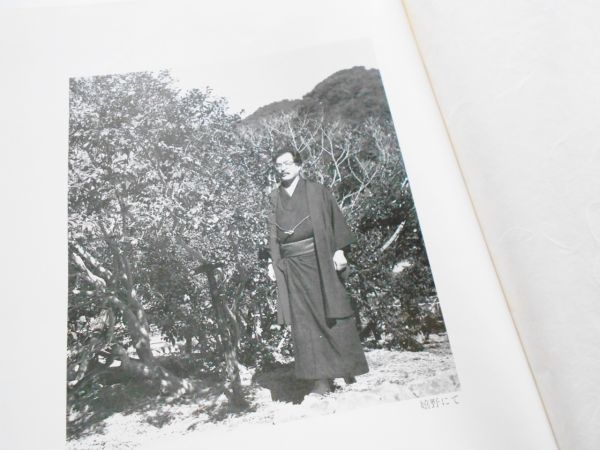













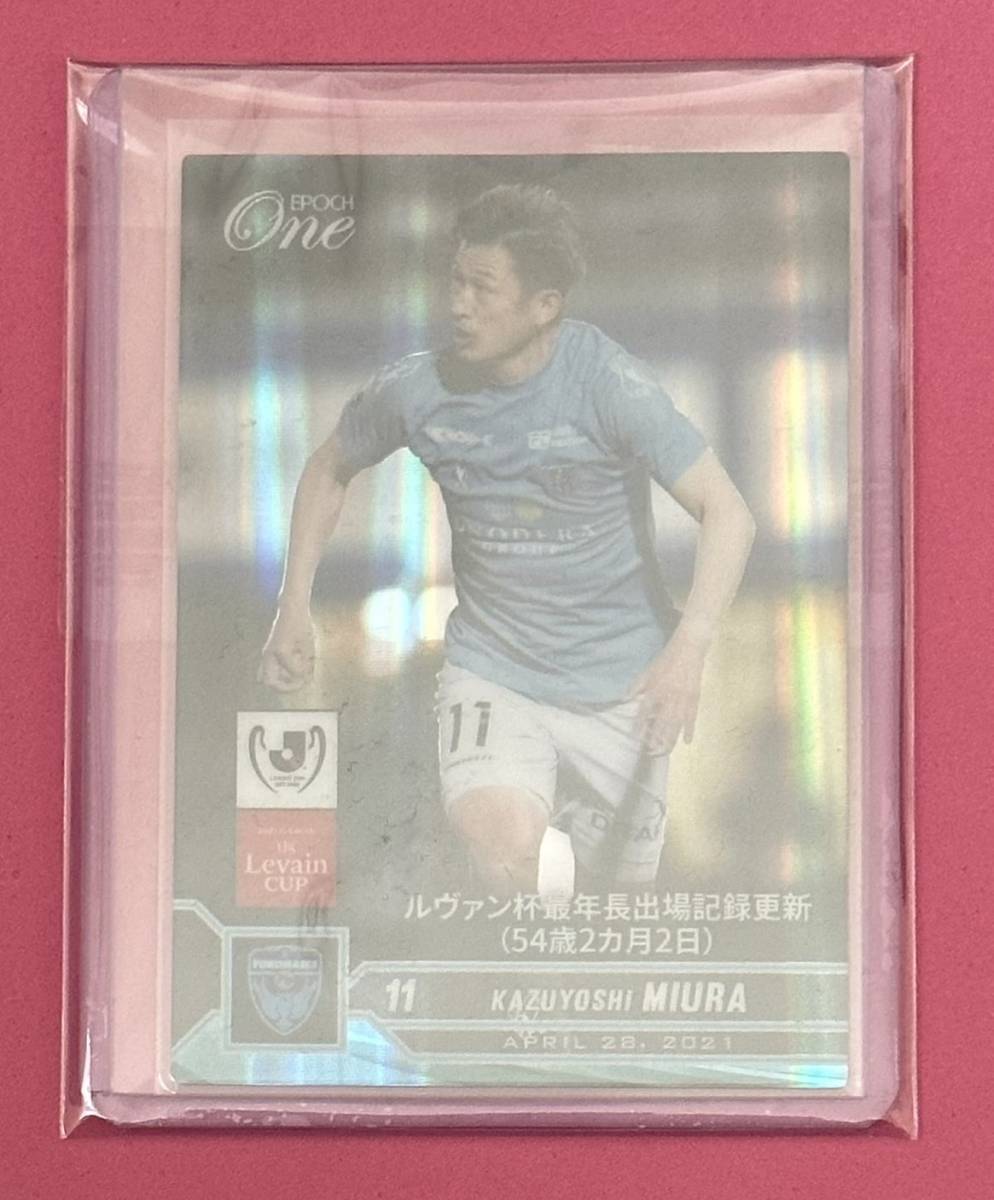










ご覧下さりありがとうございます。◆御泓軒◆『清・紫砂急須・蓮蓬荷葉紋紫砂茶壺』極細工・古賞物・中国古玩・中国古美術。中国宜興 徐美蓉 落款 在銘 紫泥 紫砂壺急須 茶壺 茶器 在銘 茶道具 時代物 中国美術 蓋裏款 朱泥 紫砂茶壺 急須 茶器 煎茶道具。